【書評】『人口減少時代の土地問題』吉原祥子

人口減少時代の土地問題 - 「所有者不明化」と相続、空き家、制度のゆくえ (中公新書)
昨日、神保町の書店で購入。面白くて一気に読んでしまった。
- 持ち主の分からない土地が増えている
- 所在不明の土地が増えることの問題点
- 所在者不明の土地が発生する原因
- 権利関係の実態と登記上の齟齬
- 解決策
- 土地は公共的な財だが…
- 銀行員時代の経験
- さいごに
- 関連記事
- 類書紹介
持ち主の分からない土地が増えている
「持ち主と連絡が取れず、処分や利用に支障をきたしてしている」
いま、日本でそのような土地が増えているという。かつては山林や耕作放棄地など、経済的価値が低いとみなされた土地が所有者不明となる場合が多かったが、最近はそれなりに価値があると思われる都市部においても「空地」「空き家」問題が深刻化している。
所在不明の土地が増えることの問題点
持ち主不明の土地が増える問題とは何か。災害復旧や耕作放棄地の解消、区画整理、公共施設の建設などといった行政サービスの行使に支障をきたすことである。実際、東日本大震災の際には被災地の復興においてこの問題が顕在化し、解決には大変なコストをかけたそうだ。
所在者不明の土地が発生する原因
所在者不明の土地が発生するのはなぜだろうか。その理由は、日本の不動産登記制度と土地にかかる強い財産権が主因であるという。
相続が発生すると、登記簿上の名義を相続人に更新する必要があるが、手続きには期限が定められていない。登記を怠ったとしても罰則はない。一方で、登記には相応の手間や金銭的負担が発生する。このため、相続登記は先延ばしにされるか、そもそも実行されないことが多い。
日本では、登記は第三者対抗要件にすぎないとされていることも相続登記がなされない理由の一つであるという。登記は不動産の権利の移転を証明するものではないため、登記をしないことで揉め事が起こりにくそうな土地については、コストをかけてでも登記を更新しようとするインセンティブに欠けるのだ。
権利関係の実態と登記上の齟齬
一方で、不動産の所有者を第三者が把握するには不動産登記簿を閲覧することが一般的であるため、登記が行われないと権利者の実態把握に混乱が生じる。「土地所有者=登記名義人=管理人」という図式が当たり前だった頃は、登記上の権利者と実態上の権利者に齟齬があっても大きな問題はなかったが、この図式が崩れ始めた今、この齟齬に起因する問題点が顕在化しているのだ。
また、日本の土地にかかる財産権は、諸外国に比べて特に強いことも問題を助長しているという。ドイツや韓国では、そもそも登記が権利の成立要件であり、権利の異動に基づいて登記を行う強いインセンティブが働く。フランスでは日本と同様登記に公信力はないものの、個人の所有権に制限を課し、必要な公的利用が円滑に進むよう制度改正が重ねられているという。
上記以外にも、固定資産税課税台帳・農地台帳などの土地情報データと、登記情報・相続情報がリンクしていないことや、地籍調査が50%程度しか進んでおらず、境界画定などに支障が出ていることなどが所在者不明の土地が生じる原因に挙げられるという。このように、土地の所在者不明問題は複合的な要因で発生しており、解決は一筋縄でいかないことが見て取れる。
解決策
本書の第4章では複数の解決策(相続登記制度の啓発、相続登記の条件緩和、登記情報へのマイナンバー紐づけによる他行政情報データベースとのリンケージ、「ランドバンク」制度の導入などを掲げているが、どれも相応の手間暇と時間がかかるものであり、短期間での解決は望みにくい。
土地は公共的な財だが…
かつては土地は何らかの利得の源泉であったが、今の日本では必ずしもそうではなくなっており、管理・継承するインセンティブが薄れている、というのが相続未登記問題の本質的な原因だろう。だが、土地は個人の財産である一方で、国土の一部であり、生産活動のいしずえであるという公共的な性格を持つものである。相続をはじめ、土地の権利にかかる問題は、個人だけでなく地域の公共の問題にもつながる問題なのである。
相続にかかる権利関係手続の面倒くささは生半可なものではないことは、私も身をもって経験している。
銀行員時代の経験
銀行員時代、預金名義人の死亡に伴う相続人から払い戻し請求にかかる事務手続きが実に大変だった。相続人が誰かを確定するために膨大な量の書類(戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書など)を用意する必要があり、銀行・顧客双方に多大な手間がかかる。土地の場合もおそらく似たような事務負担が発生するものと思われるが、莫大な手間暇をかけても得られるのはコストばかりかかる『負動産』であるとなると、承継したくなくなるのも当然であろう。
銀行と預金者の関係は、いち企業と個人の問題にすぎないが、先述したように土地は公共性の強い財であることを考えると、土地の権利を他の財と同等に扱うのは不適当かもしれない。相続手続きの簡素化や収容条件の緩和など、土地の権利については私権をある程度制限する必要があるかもしれない。
(少し話はそれるが、土地は公共的な役割を持つという前提に立つならば、サンデル先生にいわせると、コストがかかることを理由に土地の管理を放棄することは公共心の欠如ということになるのだろうか)
さいごに
土地の権利にかかるシステムは制度疲労を起こしており、時代にそぐわなくなっているというメッセージを本書から読み取った。何らかの手立てを打たないとこの問題らより問題は深刻化していくだろう。地方行政や国土行政に関係する人や、不動産を持つ人は「我が事」ぜひ読んでほしいと思う。
私もいずれ実家の土地建物を相続する身であり、本書の議論は他人事ではない。「公民」として財産回りの手続きはキッチリとしておこう、という思いをあらたにさせてくれる一冊であった。

人口減少時代の土地問題 - 「所有者不明化」と相続、空き家、制度のゆくえ (中公新書)
- 作者: 吉原祥子
- 出版社/メーカー: 中央公論新社
- 発売日: 2017/07/19
- メディア: 新書
- この商品を含むブログ (1件) を見る
関連記事
類書紹介

未来の年表 人口減少日本でこれから起きること (講談社現代新書)
- 作者: 河合雅司
- 出版社/メーカー: 講談社
- 発売日: 2017/06/14
- メディア: 新書
- この商品を含むブログ (8件) を見る

人口と日本経済 - 長寿、イノベーション、経済成長 (中公新書)
- 作者: 吉川洋
- 出版社/メーカー: 中央公論新社
- 発売日: 2016/08/18
- メディア: 新書
- この商品を含むブログ (17件) を見る
【書評】『それをお金で買いますか 市場主義の限界』マイケル・サンデル
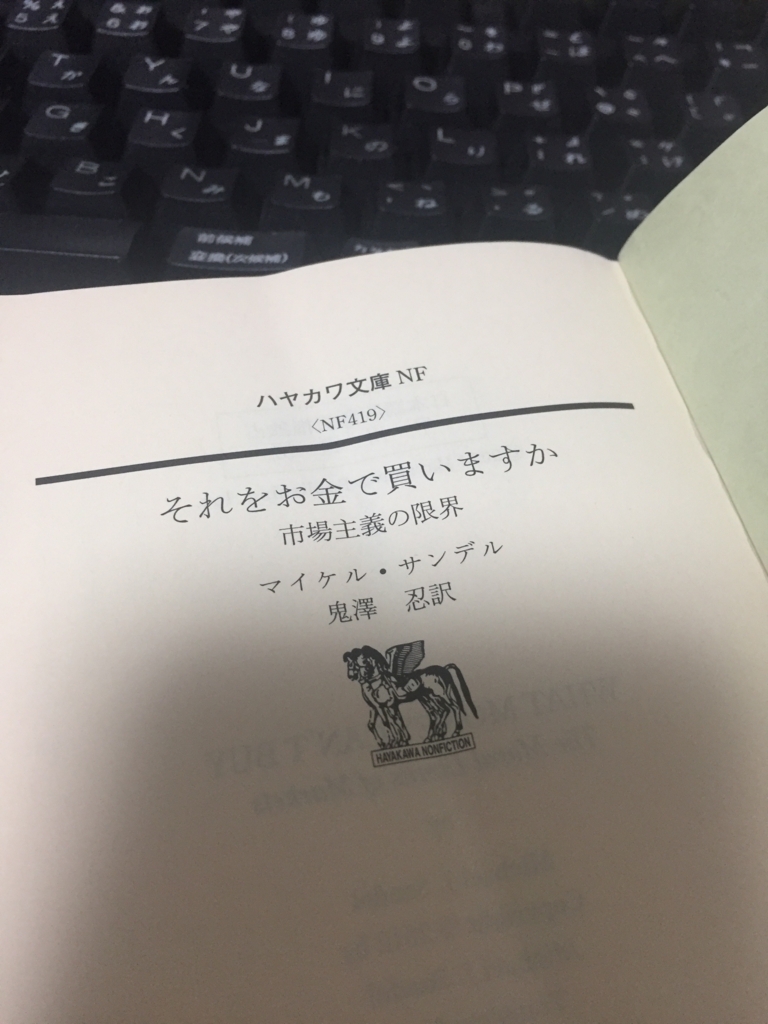
昔(今もあるのかもしれないが)、「お金で買えない価値がある。買えるものはマスターカードで」というCMがあった。
恋人の誕生日を祝うにあたり発生する様々なコスト(タクシー代、誕生日プレゼント代、高級レストランでの食事代)といったものは金で買えるが、「恋人の誕生日を祝いたい」という気持ちやそれに付随する感情は金で買えない~という内容のCMである。
我々は、世の中に金で買えるものとそうでないものの2種類があることを知っている。鉛筆、不動産、スマートフォンは金で買えるものである一方、親子の絆、誇り、貞操観念、公徳心などは金で買えないもの…そういう認識が一般的であろう。
しかし、後者もカネで買おう、お上品に言い換えるなら後者に「インセンティブ」を与え、「マネタイズ」しよう。そのほうが世の中にとって良いはずだーーそのような考えに「それって本当にいいの?」と本書は問いかける。
著者であるサンデル氏は、本書の目的をこう定義する。
お金で買うことが許されるものと許されないものを決めるには、社会・市民生活のさまざま領域を律すべき価値は何かを決めなければならない。この問題をいかに考えぬくかが、本書のテーマである(p23)
そもそも、なぜ『お金で買うことが許されるものと許されないもの』があるのだろうか?著者は、その理由を二つ挙げる。一つは「不平等に関わるもの」であり、もう一つは「腐敗に関わるもの」である。
まず、「不平等である」とはどういうことか。それは、「お金を持っていることがあらゆる違いを産み出すことになり、不平等の刺すような痛みがいっそうひどくなる」ことである。社会格差が拡大することで、市民社会に分断が生まれ、それが大きくなることを危惧しているのだ。
「政治的影響力、すぐれた医療、犯罪多発地域ではなく安全な地域に住む機会などがお金で買えるようになるにつれ、収入や富の分配の問題はいやがうえにも大きくなる」(p21-22)。
「腐敗」とは何を意味するか。
「生きていくうえで大切なもののなかには、商品になると腐敗したり堕落したりするものがある」(p24)。
世の中にはお金の力がおよぶ「べきでない」領域が存在する。健康、教育、自然、芸術などがそれである。本書は、この2つのテーマを根底に据えたうえで、
「公共生活や人間関係において市場が果たすべき役割は何か」「売買されるべきものと、非市場的価値によって律せられるべきものを区別するにはどうすればいいか」(p25)
について、様々な具体例を挙げて読者に考える機会を提供するという構成となっている。
少し話がそれるが、私は大学を卒業してから今に至るまで、一貫して金融業界で飯を食べてきた。金融-市場メカニズムをある程度「当然」とし「是」とする価値観の中でメシを食ってきたし、今後もそうだろう。そのような自分にとって、「市場メカニズムは決して万能ではなく、それが馴染まない分野は山のようにある」という本書の主張は「ああ、そう言えばそうだよなぁ」という納得感をもたらしてくれた。同時に、「市場メカニズムは善であり、万能の処方箋である」という規範に知らず知らずのうちに侵されていたなぁ、という自覚に至り若干慄然とした。
そもそも、市場メカニズムが善とする「効用を最大化する」というお題目も、功利主義の一形態であり、他の道徳的規範に比べて優劣を付けられるものではない。考えてみればシンプルな話である。
一方で、我々の意思決定-ー個人レベルであれ社会全体であれーーは、「市場メカニズムこそが善である」という前提でなされることが増えている、ということに著者は警鐘を鳴らしている。
裁判の傍聴券を得る代わりに、誰かに金を払って並んでもらうことは「裁判の傍聴」という行為の趣旨になじむのか。
教育的効果が認められるからと言って、子供が宿題を仕上げるたびに小遣いをやることは正しいのか。
罰金を支払いさえすればスピード違反をしてもよいのか。
--など、市場メカニズムと道徳を巡る問題は色々な局面で表面化しつつあり、本書には(主にアメリカで)その極端にはしった事例が数多く紹介されており、大変興味深い。
よりよく生きるとは、市場メカニズムのもたらす価値観に適応的であることなのか?決してそうではない、ということを気づかせてくれる良著である。
同じ著者による類書はこちら。

これからの「正義」の話をしよう (ハヤカワ・ノンフィクション文庫)
- 作者: マイケルサンデル,Michael J. Sandel,鬼澤忍
- 出版社/メーカー: 早川書房
- 発売日: 2011/11/25
- メディア: 文庫
- 購入: 4人 クリック: 204回
- この商品を含むブログ (78件) を見る
【書評】『"羽田の空"100年物語』近藤晃

大学で歴史学を学んだということもあってか、私は身近な事物の歴史を知ることが好きだ。全ての物事につき、過去の行いや決断の積み重ねの結果として「いま」がある。だから、ある物事をよく知るためにはその物事の由来を知るのが最良である-こういう風に思っている。
また、私は乗り物、特に旅客機やそれにまつわる色々なものが好きだ。旅客機は見た目が恰好いい。旅客機に乗って空を飛ぶこともワクワクして楽しい。加えて、旅客機の開発・運行・整備や、その進歩の歴史は、そのまま人類の英知の発展の歴史であり、知的好奇心を刺激されてやまない。
という訳で、旅客機の歴史にはもともと関心があったところ、職場の近くの本屋で本書『“羽田の空”100年物語: 秘蔵写真とエピソードで語る (交通新聞社新書)』を見かけて購入した次第である。
本書は、タイトルの通り、羽田空港の開港から現在に至るまでの歴史を、豊富な写真で振り返るものである。今年(2017年)は大正6年(1916年)に羽田町・穴森に「日本飛行学校」が開校してからちょうど100年を迎えるという。同校が開校したころの羽田の地は、遠浅の海岸を利用した海苔の養殖や魚介類の漁が行われる風光明媚な漁村であったそうだ。同校の設立場所に当地が選ばれた経緯は本書には触れられていないが、潮が引くと広大な砂地が出現するという地形が選定理由だったのかもしれない。
その後、日本が国力を増大させ、また飛行機の技術が進歩するとともに、羽田空港は大日本帝国の帝都・東京の玄関口として急速に拡大していく。国内の航空路線網は言うに及ばず、昭和15年には東京~バンコク間の定期航空便が開設されたという。
敗戦とともに、羽田空港はGHQに接収され「ハネダ・エアベース」と呼称されるようになる。「ハネダ」が「羽田」に戻るには、サンフランシスコ講和条約が発効し接収が解除される昭和27年まで待たねばならなかった。
日本の国際的地位の回復と経済成長に伴う航空輸送需要の拡大や、航空機の大型化といった要因に促され、羽田空港は拡張工事を重ね、現在の体制(4本の滑走路、3棟のターミナルビル)に落ち着く訳だが、本書が面白くなるのは話が昭和50台ごろに差し掛かってからである。著者の近藤氏が撮りためた秘蔵写真が一つ二つと開陳され出すからである。
近藤氏は、昭和50年から職業カメラマンとして羽田空港の写真を撮り続けてきており、一般人が撮影できない場所から撮影する機会にも頻繁に恵まれたそうだ。各国のVIPが東京を訪問した際に撮影した写真や、羽田空港の拡張工事を間近でとらえた写真が本書に多数掲載されている。どれも貴重なものである。
昭和61年5月にミッテラン大統領大統領一行を載せて飛来した際に撮影された、エールフランスのコンコルド2機が写った写真や、平成2年にチャールズ皇太子とダイアナ妃が来日した際に、「JAL」のロゴが入ったタラップを降りる写真などが興味深い。羽田空港は、成田空港が開港してからも、東京中枢部に最も近い空港は羽田空港であることに変わりなく、東京を訪れる要人にとっての「玄関口」であり続けたのである。
上述したように、本書では羽田空港の歴史にかかわる写真が多数紹介されており、読んでいて飽きがこない。年に数回でも、羽田空港を利用する機会がある人は、きっと興味深く読めることと思う。

“羽田の空”100年物語: 秘蔵写真とエピソードで語る (交通新聞社新書)
- 作者: 近藤晃
- 出版社/メーカー: 交通新聞社
- 発売日: 2017/02/15
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
なお、類書として本書『航空から見た戦後昭和史:ビートルズからマッカーサーまで』も紹介したい。こちらのほうが内容は遥かに濃く、掲載されている写真の稀少度も高い。ぜひ手に取っていただきたい一冊である。
扱う対象は航空機に限定されないものの、「時刻表の変遷から近現代の世界史を読み解く」 というユニークな切り口の本書『時刻表世界史―時代を読み解く陸海空143路線』もオススメである。
戦前~戦中にかけての日本の外洋交通について興味がある方には、本書『帝国日本の交通網: つながらなかった大東亜共栄圏』もお勧めしたい。
【書評】『戦艦大和の最後~一高角砲員の苛酷なる原体験』坪井平次

戦艦大和の最後―一高角砲員の苛酷なる原体験 (光人社NF文庫)
終戦記念日と被ることもあり、毎年7~8月にはできるだけ戦争関係の本を多く読むようにしている。7月末に実家に帰省したおり、実家の自室の書架から本書を見つけたので持って帰って読むことにした。(中に挟まっていた栞に印刷されていた美術展の広告から察するに、高校生の頃に買い求めたものらしい。一度は読んでいると思うのだが、全く内容が記憶にない)
本書は、著者である坪井氏が徴兵されて戦艦「大和」所属の兵卒として従軍し、終戦を経て除隊するまでの一連の出来事を綴ったものである。
大正11年に三重県熊野市で生まれた坪井氏は、昭和17年に三重県師範学校を卒業したのち郷里の国民学校の訓導(教師)となる。昭和18年4月に徴兵され海軍に入り、戦艦「大和」配属となり五番高角砲員となる。マリアナ沖海戦、レイテ沖海戦を経験したのち、沖縄特攻作戦に従軍。「大和」の沈没に巻き込まれるも九死に一生を得る。終戦後は教師として復職し、のちに校長を務めるなど教育界で大いに活躍されたようだ。
従軍してからの顛末は、それまでの平穏な日々の描写と同様、淡々とした書きぶりで綴られているのが印象に残った。戦争が終わって何年も経ち、自身の経験した苛烈な経験を冷静に振り返ることができた、ということなのだろうか。
その淡々とした筆致は、本書で最もハードな場面においても変わらない。「大和」沈没後に漂流していたところを、僚艦であった駆逐艦「雪風」に救助されるシーンである。「雪風」からたらされたロープにやっとの思いで掴まったものの、
私の足にしがみついてきた者があった。私は、見栄も外聞もなく、足を振ってその手を逃れたのである。生死の関頭に立たされた私のエゴであった。気の毒だが、やむを得ない。許してくれよと、心中でそう詫びた。(P274)
芥川龍之介の『蜘蛛の糸』を髣髴とさせるシーンである。これ以上の修羅場があるだろうか。このような経験を書き残すのは大変な心理的重圧があったものと推察するが、事実を書き残した著者の勇気には感服せざるを得ない。
三重県の片田舎で教職を務めていた坪井氏は、戦争さえなければ本書で綴られるような過酷な体験をすることなく、平穏無事に一生を過ごせたことであろう。それだけに、「徴兵」というシステムで国民の人生を翻弄する国家権力の暴力性には慄然とさせられる。

戦艦大和の最後―一高角砲員の苛酷なる原体験 (光人社NF文庫)
- 作者: 坪井平次
- 出版社/メーカー: 光人社
- 発売日: 2005/03/01
- メディア: 文庫
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (1件) を見る
【書評】『在日マネー戦争』朴一

職業柄、金融関係のドキュメンタリー本を折をみてはチビチビと読んでいる。その多くは日本の大手金融機関を扱ったものだが、今回紹介する『在日マネー戦争 』は、在日コリアンが設立した金融機関を取り上げているという点で若干毛色が事なる作品である。
本書は、戦後の大阪を舞台に、在日金融機関の設立・再編を巡る歴史と、それに纏わる人間ドラマを綴ったものである。物語は、焼き肉屋が所狭しと立ち並ぶ日本屈指のコリアタウン・鶴橋から始まる。当時の鶴橋一帯は猪飼野と呼ばれ、生活の糧を求めて朝鮮半島から渡ってきた移民労働者が多く居住する地域であった。
戦後、当地には闇市が立ち並び活況を呈することとなるが、やがてイリーガルな闇市ではなくきちんとした商行為が行われる「商店街」に生まれ変わらせようという機運が生まれる。この商店街結成にイニシアチブを取ったのが李熙健という男である。彼は鶴橋でゴム業を営む傍ら、高利貸しも手掛けていたことから、後に在日韓国人系の信用組合である「信用組合 大阪興銀」を設立することとなる。在日韓国人たちが自前で金融機関を設立した背景には、日本の金融機関の在日韓国人に対する消極的な取引姿勢があった。
「在日コリアンはやがて帰国するかもしれない」という思惑のほか、少数民族問題の種となることを恐れて在日コリアンを祖国に帰国させたい日本政府と、彼らの祖国への帰国問題を戦後補償の政治カードとして利用したいと考える韓国・北朝鮮両政府との間で日韓・日朝交渉が難航しており、在日コリアンの法的地位が流動化しているという政治情勢があった*1
かくして、日本一小規模な信用組合としてスタートした大阪興銀が最初に手を付けたのは預金の獲得であった。金融機関が事業を拡大するには、何を差し置いても投融資の原資である預金を大量に集める必要がある。理事長に就任した李は、職員に厳しい預金獲得ノルマを課し預金獲得競争に明け暮れた。その苛烈なエピソードは読んでいて胃痛を催すほどである(笑)。
大阪興銀の融資姿勢は、日本の金融機関が「リスクが高い」として忌避してきたビジネスに積極的に融資するというものであった。焼き肉店、パチンコ、ファッションホテル、ソープランドなどがそれである。
各支店から在日コリアンの職員をそれぞれの現場に派遣し、そこで実際に働かせることで、徹底的に在日の商店や企業を研究させ、「担保不足でも貸せるかどうか」の業種別の融資基準を作らせた。この結果、たとえ担保がない場合でも、焼肉のタレの味やパチンコ台の性能を担当者が評価して融資することが、大阪興銀では可能になった(キンドル版 位置750)
…と、今はやりの「事業性融資」を先取るような事業戦略を取っていたことを伺い知ることができ興味深い。このほかにも、大阪興銀はあの手この手で顧客を獲得し業容を拡大していくのだが、その手法についても本書で詳しく説明されており、「なるほど」と唸らされる。金融機関職員が読むと色々と気づきや学びがあるだろう。
このように、日本の金融機関にはみられない(というかマネのできない)ユニークな事業戦略で拡大を続けてきた大阪興銀(合併を経てのちに「関西興銀」となる)だったが、紆余曲折を経たのち2000年に破綻し一旦その歴史を閉じることとなる。
戦後から現在に至るまでの、在日韓国人系金融機関の興亡史は、そのまま在日韓国人が現在にいたるまで積み重ねてきた労苦の歴史であるといえるだろう。月並みだが、祖国を離れた地で生き抜くことの大変さをしみじみと語りかけられるような読後感だった。加えて、いかに商業的に成功しようとも、決して日本のエスタブリッシュメントの一員として迎えいれられることのない屈辱感を、世間一般に正業とされる「金融機関の設立」でもって拭おうとした、という読み方もできると思う。
歴史や政治に翻弄され続けた在日コリアンの悲しい歴史を、「金融」というユニークな切り口から著した良著である。皆さんにもぜひ読んでいただきたい。





